|
地震や台風のとき発生する水平力に耐えられるように、地震力に対しては建物の床面積、風圧力に対しては外壁の見付面積の大きさ、
それぞれに応じた耐力壁が必要とされる。 我が家の場合、設計段階での耐震性の壁倍率は必要壁量の平均1.95倍(1階)、2.88倍(2階)、偏心率は平均2.7%(1階)、 3.8%(2階)になっており、計算上では品確法の3等級を超えるのでOKとされる。 木造軸組みではツーバイフォー工法(すべての壁が耐力壁に出来るため壁倍率も大きくできる)に比べて壁倍率が少な目に表示されるが、 これは管柱間に張った室内石膏ボードの壁倍率(1.0)を計算に入れていないこと、太い柱や梁でも耐力を保っている、 など元の基準が異なるので比較にはなりにくい。 しかし住友林業では壁倍率や偏心率のことを強いて言うことはなかった。 数値による評価は目安程度のものということだろうか。 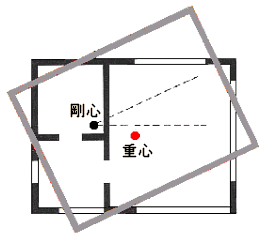 耐力壁は基礎と柱と梁が、筋交いや耐力合板と一体化して耐力を示すので、局部的な耐力よりも家全体でのバランスが重要であり、
壁倍率が高くてもそれが偏っていると偏心率が大きくなり、かえって危険が増す。
したがって壁倍率の数値だけでは判断できない。
耐力壁は基礎と柱と梁が、筋交いや耐力合板と一体化して耐力を示すので、局部的な耐力よりも家全体でのバランスが重要であり、
壁倍率が高くてもそれが偏っていると偏心率が大きくなり、かえって危険が増す。
したがって壁倍率の数値だけでは判断できない。更に耐力壁は高い壁倍率を使って最小枚数にするより、 小さい倍率の壁を家全体にバランスよく多く配置した方がよいと言われている。 偏心率は家全体の剛体バランスを示す値で、これによって地震力の影響を受け易いか否かが変わってくる。 地震力は建物の重心に作用すると考えられ、地震で外部から水平力が加わると剛心(建物の強さ)を中心に建物の重心が振り子のような回転運動をするようになり、 その結果として地震エネルギーの集中を受けた箇所は耐力が低下し損傷へと繋がっていく。 したがって、剛心と重心の距離は短い方が揺れは少なく地震の影響も受けにくいことになる。 上図は耐力壁のバランスが悪く剛心が重心の左側に偏っているが、右下方面の外壁に耐力壁を増せばバランスが整ってくる。 つまり剛心が重心に近づくように耐力壁を配置すればバランスよく地震による変則的な揺れは少なくなると言うもの。 逆にその距離が離れすぎると大きく揺れて、どこかに共振点が発生するようになると壁倍率が高くてもその破壊力には耐えられなくなってしまう。 以前にテレビで「五重塔はなぜ地震に強いか」を伝えていたが、これも偏心率が非常に小さいことを示した証だろうか。 2000年の建築基準法改正で木造住宅の偏心率は30%以下にするよう規定されたそうだが、安心のためには15%以下が望ましいという。 因みに我家の偏心率は計算上、平均2.7%(1階)、 3.8%(2階)になっていた。 |
|
耐震性の検証として住友林業のパンフレットでは、阪神淡路大震災に観測された最大加速度800ガルを想定して、
それより大きい1,000ガルの水平揺れを1階基礎部分に2回与えたが倒壊することなく安全であったと記載してある。
では、2005年の新潟県中越地震のように場所によって1,200ガル以上で揺れた場合はどうなるのだろうか(地盤の緩い地域では更に揺れたという)。
建築基準では400ガル程度の揺れに対して倒壊・崩壊しないことにしている。 メーカーの建てる住宅の耐震性はさらに高く、
品確法の3等級(建築基準の1.5倍)をクリアーしているというが、それでも僅か600ガル程度の揺れに耐えるぐらいであり、
同じ地域でも建てる場所の地盤によってはこれで安全とは言い難いようだ。 阪神大震災の倒壊原因の代表的なものに耐力壁の不足が挙げられていることから、 壁倍率と偏心率は品確法の等級3を満たしても物足りないかもしれない。 中越地震は震度6から5の余震がいくつもあったそうで、新築の時は耐震性能が等級3であったものが、 余震により耐力壁のクギやビスの効きが甘くなり次第に等級2から等級1へと性能が劣化していくことも考えられるため、 品確法の等級3は地盤の状況によっては耐震構造として安全圏ではないようだ。 新潟県中越地震では皮肉にも建築基準法を守った住宅の多くが倒壊し、 地域の特性をよく知り安全率を充分にみて建てた家は倒壊しなかったという。 家を建てる地域の地盤の影響は大きく、地盤が軟らかいときにその周りだけを地盤改良して建てる場合と、 岩盤のような硬い地盤上に建てる場合で地震波の伝わり方が違うだろう。 柔らかい地盤では地震波の伝わる振幅が大きく建物の揺れも大きいが、 地層が硬く岩盤のような地盤では地震波の伝わる振幅が小さく建物の揺れも少ないことは容易に想像できる。 |
|
コンクリートは圧縮に対する抵抗力が強い反面、引っ張り力に弱く、これを補うため引っ張り力に強い鉄筋を組み合わせることによって耐震、
耐久、耐火性の高い構造体にすることができ、今のところ鉄筋コンクリートに変わる良い素材は存在していないといわれる。 鉄筋は非常に錆やすいが、アルカリ性であるコンクリートで内部を包み込むことによって安定している。 また、鉄筋は高温になると強度が急激に低下し900℃前後で強度を失ってしまうのをコンクリートで保護することによって耐火構造にもなっている。 コンクリートはセメント・川砂・川砂利(骨材)・水を組み合わせて作るので、これらの材質や使用比率で強度や耐久性が変わってくる。 その中で、水セメント比(W/C)は小さいほど強度の高いコンクリートになり、中性化のスピードが遅くなるため永く強度を保つが、 あまり水の量を少なくすると粘性が強くなって施工が難しくなる。 建築基準では水セメント比は65%以下と定められているそうだが、 鉄筋コンクリートの耐久性を高めるためには水セメント比は50%弱にするのがよいと言われる。 |
コンクリートは打設当初は強いアルカリ性をもち水や空気によって鉄筋が錆びるのを防ぐが、
次第にコンクリートの中性化が進行し、鉄筋に達すると急に錆びるようになり、
錆びはじめると膨張してやがて爆裂したとき、伸張に弱いコンクリートに亀裂が生じ強度を落とすことになる。
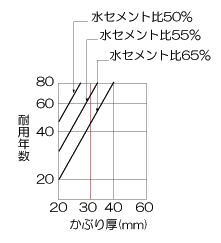 このため鉄筋を包み込むコンクリートに厚み(かぶり厚)を確保する必要があり、
そのかぶり厚も土に接する面は厚くした方が好ましいようだ。
このため鉄筋を包み込むコンクリートに厚み(かぶり厚)を確保する必要があり、
そのかぶり厚も土に接する面は厚くした方が好ましいようだ。鉄筋コンクリートの耐用年数を維持するため水セメント比を少なくすることによって中性化の進行を遅らせることができる。 右図を見ると水セメント比によって耐用年数とコンクリートかぶり厚の関係が分かる。 たとえば水セメント比50%のコンクリートを使用した場合にかぶり厚30mm程度あれば中性化が進んで鉄筋に錆が出るまでに100年位かかる、 つまり耐用年数は100年位あることになる。 昔よく使われていたそうだが、水セメント比を65%のコンクリートで、 そのかぶり厚にすると施工はやり易いが耐用年数は40年強ということになる。 通常は水セメンと比50%弱、かぶり厚40mm(建築基準)〜50mm以上で施工されるようだ。 |